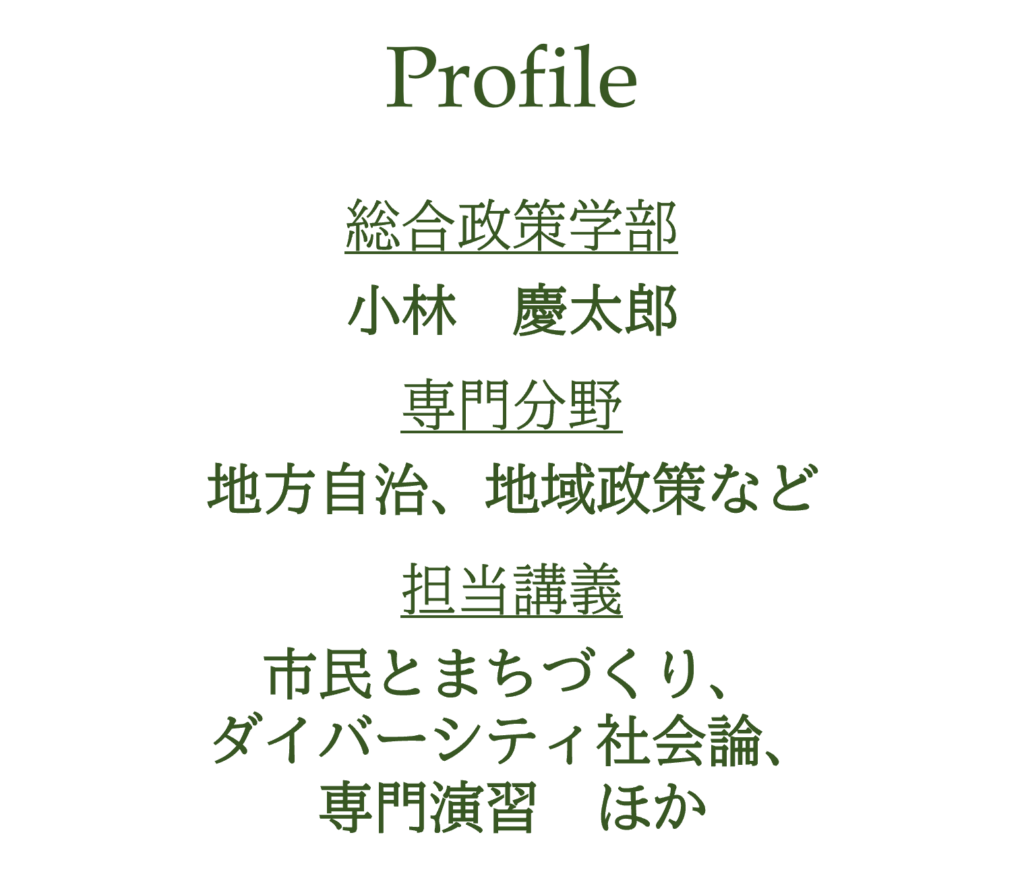政策は誰が決めているか?
世の中で起きる様々な問題。その解決策が政策です。ではその政策は、誰が考えて、誰が決定するのでしょうか。民主主義なんだから、当然、みんなで考えて、みんなで決めれば良いんでしょ! そう思われるかもしれません。でも実は、そこに落とし穴があるんです。
例えば、高校の文化祭でのクラスの出し物をどうやって決めるか、を想像してみましょう。演劇、お化け屋敷、クレープ屋…。いろんなアイディアが出てくるかもしれません。でも、よーく見てみると、みんなが発言しているわけでもなさそうです。クラスを仕切っている一部の声の大きな人に流されていませんか? 「それは仕方ないよ。最後は多数決で決めるんだから一応みんなの声は反映されているし…」。まぁ、そんな見方もあるかもしれませんね。さて、このクラスでは、多数決でクレープ屋さんをやることになりました。一応、みんなで考えて、みんなで決めたので、あとは準備を進めていくだけ…。ところが、ここで、困った事態が。小麦アレルギーがあるので参加できないと言う生徒が現れたのです。みんなで考えてみんなで決めたはずなのに…。いったい、どうすれば良かったのでしょう。
実は、これと同じようなことが、学校の外、大人の世界でも起きています。声の大きな人たちが、声高に主張する一方で、自分の考えがまとまらない人や意見を十分に表明していない人もいます。声の大きな人に流されることで、弱い立場の人が辛い思いをしてしまっている場面もあります。
政策はどうやって決めたら良いのか
さて、そこで、実際に政策をどう決めていったら良いのかという方法を考えていくことが、一つの研究課題になります。いわゆる民主主義国家では、代議制民主主義という方法が多く採られています。選挙で代表を選出して、その代表が話し合って、最終的に多数決で決める、といったやり方ですね。
でもこの代議制民主主義では、実は、先に挙げた、声の大きな人に流される問題も、弱い立場の人が辛い思いをする問題も、十分には解決することが出来ていません。そもそも、政治家として立候補して当選する人は、ある程度大きな団体などに推されている人が多く、一方で、一般の学生とか会社員は、なかなか立候補もしづらいですよね。
そこで、これまでにも、地方自治体では、一般市民の意見を反映させるための様々な方法が考えられ、そして試みられてきました。アンケートや意見募集や住民投票などです。そうした中で、最近注目されているのが、ドイツで行われているプラーヌンクスツェレという方法を真似た、市民討議会という手法です。無作為抽出で集められた市民による熟議で政策を考えていくという手法なので、声の大きな人だけではない市民の声が反映されやすいといったことが期待されています。これまで私は、こうしたやり方を研究し、実際に愛知県内の地方自治体の条例にこの手法を明記し、実装していくことを進めてきました。
-1024x683.jpg)
愛知県Ⅰ市での市民討議会の様子(中央に立っているのが小林)
誰もが辛い思いをしない政策は
こうした政策決定のプロセスを考える一方で、これまで私は、決定される政策の中身についても考えてきました。世の中で、もし誰かが辛い思いをしているのだとすれば、それを解消できるような、誰もが辛い思いをしなくて済むような政策が、必要でしょう。
例えば、LGBTQなどと称される性的少数者。性の多様性に対する理解は、ある程度進んできてはいますが、まだまだ地域で職場で偏見や差別にさらされ、家庭を築き平穏な日常を送ることが出来ていない人たちがいます。そうした状況を改善していくために、出来ることはないのか。
私は、三重県が性の多様性に関する条例を作る際に、有識者としてその検討会議の座長を務めるとともに、現在は、三重県男女共同参画審議会の委員として、性の多様性に関する三重県の取り組みを後押ししています。
これからも、政策決定のプロセスや中身がより良いものになっていくよう、積極的に社会に関わり実践しながら、研究も進めていければと思っています。