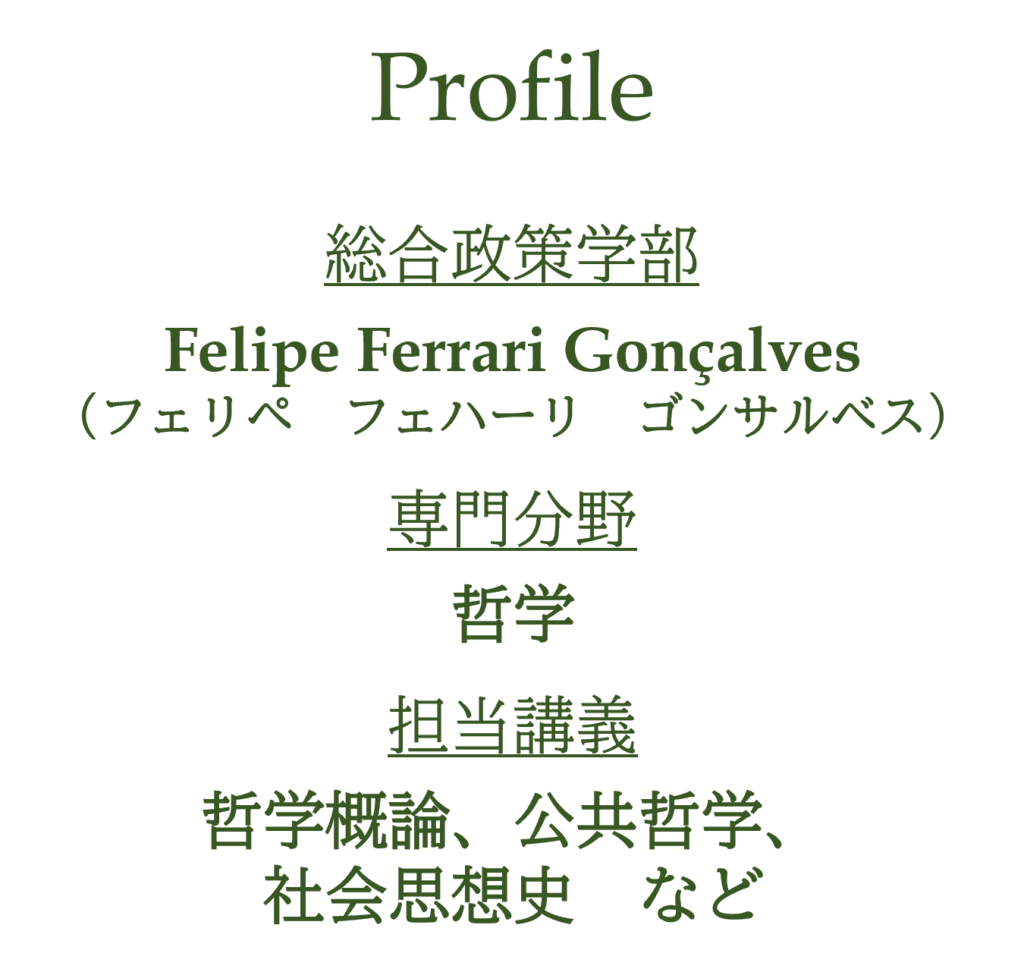京都学派
「哲学」(元々は「希哲学」)という単語が、1874年に西周(1829−1897)によって作り出された。しかしながら、本当の意味での日本の哲学的伝統は、20世紀初めに西田幾多郎(1870−1945)の『善の研究』が出版されたことと共に始まったといえる。この著作で西田は、自身が、東洋の宗教や文化、西洋の文学や哲学の双方から大きな影響を受けたことを顕にしており、彼は、西洋哲学の方法に禅仏教の様々な特徴を組み入れたわけである。そして、「京都学派」という、西田から始まる哲学的伝統は、太平洋戦争勃発を経て戦後に至るまでの時代には動揺を余儀なくされたとはいえ、1945年に西田が没した後も、鈴木大拙貞太郎(1870−1966)、田辺元(1885−1962)、和辻哲郎(1889−1960)、三木清(1897−1945)、西谷啓治(1900−1990)、阿部正雄(1915−2006)、上田閑照(1926−2019)などによって継承されていったのである。
京都学派に見られる顕著な特徴の一つとして、彼らの深い宗教的影響(とりわけ禅仏教からの影響)を挙げることができる。実際、このような宗教的バックグラウンドは、『善の研究』出版以前の西田の思想においても見出すことができる。また、「宗教」と「神」の観念についていえば、それは西田の生涯の思索を貫いているのであり、さらに、これらの観念は他の京都学派の哲学者の思想においても根本的な役割を担っているのである。
田辺元の思想
現代社会においては、世界の各地での戦争の恐れが存在しているため、田辺の思想を研究することが重要である。第二次世界大戦の末期に著述され、1946年4月に出版された『懺悔道としての哲学』においては、田辺は戦後の社会のための新たな哲学を提案した。哲学者として、教師として、そして人間として、おのれの力が罪悪に抵抗するのに足りないと理解したとき、懺悔が田辺の中に起こった。つまり、懺悔とは、自己の無力不能が犯した重大な避けられない罪をすべて悔い改めることである。このような自己の無力のゆえに、田辺は哲学に新しい概念を与えたのであり、その概念は、自力の理性に基づくものではなく、懺悔に自己を導く他力に基づくものである。もはや自己が理性的思考を通じて哲学を求めるのではなく、むしろ、懺悔が自己を通じて哲学を考えなければならないのである。すなわち、田辺は、伝統的哲学の拒絶から生まれてくる新たな哲学――すなわち、「哲学ならぬ哲学」――を求めているのである。
懺悔道としての哲学
田辺における懺悔の道は個人的なもののみではなく、社会全体が行わなければならないものである。彼によると、個人は社会的環境に責任を負っており、そして社会に善行をなすために最良の方法は懺悔道を通じて罪悪を悔い改めることであるからだと言える。第二次世界大戦というコンテクストにおいて田辺の考え方は容易に理解することができる。つまり、個人の懺悔によっては、日本が戦争で犯した罪悪を償うことはできないが、もしすべての日本人が、戦争の頃の個々人の無力を悔い改めたならば善行の社会が作れるようになるわけである。
懺悔道の基礎は自己が犯したあらゆる罪悪の絶え間ない回想である。その回想は自らの罪悪の回復不能性の確実性、および他人や社会全体に善行をなすことを必要とすることに至る。田辺によれば、自己が存在するため、「我証」が存在し、我証というのはすべての悪の原因なのである。そのため、キリスト教の原罪という概念と同じように、自己の存在そのものが罪であり、人が善行をなすことができる方法は絶え間ない懺悔のみである。人は自分のためではなく、他人や社会のために生きなければならない。
自己の役割
自らの無力の認識による自己の「死」の後に、完全におのれを懺悔に捧げている自己が誕生する。その新たな自己は、「空有の存在」として、絶対無を媒介するものである。それは、無即愛として自己であり、懺悔道の中心である。すなわち、懺悔が自己から開始し、他力が自己に作用を及ぼす。そのため、自己が他力に落ち込むということは、田辺哲学において自己には何の役割もない、ということを意味するわけではない。むしろ、自己の役割は懺悔を行い、他力に落ち込むことを求めることにある。さらに、懺悔は自己の絶え間ない作用でなければならない。もし、自己が懺悔を辞めたならば、人はもう一度自力を信頼するようになってしまうため、再び最初から悔い改める習慣をつけなければならない。つまり、田辺における懺悔というのは、一度きりの反省あるいは片ときの絶望ではなく、自らの無力不自由の絶え間ない確言であり、罪悪の絶え間ない悔いである。
参考文献
−田辺元:『懺悔道としての哲学―田辺元哲学選II』.岩波書店,2010.