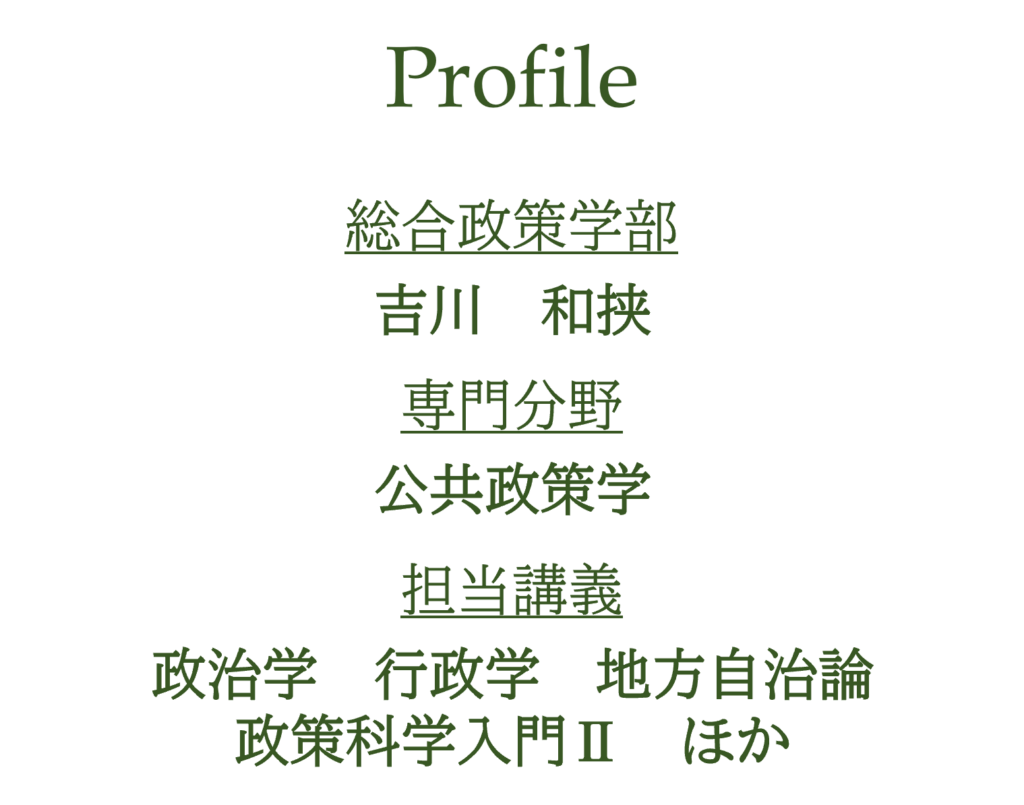政策の成功とはなにか?
実は「政策の成否」というのは判断するのが非常に難しいものです。というのも、どれだけ客観的に効果の出た政策であっても、その政策を推進した政治家や政党、あるいはその政策自体をそもそも支持していない人にとっては「あの政策は失敗だった」と感じられるものだからです。
ここから引き出せる含意が大きく二つあります。一つは世の中には価値観の異なる人が数多存在し、政策は必然的に価値観の異なる人同士での対立の渦中に投げ込まれてしまうということ。もう一つは、だからこそ政策の成否は必ずしも客観的なデータなどの指標「のみ」によって判断できないということです。政策を成功させたいと望むなら数値目標を達成することを大前提としつつも、社会に存在する人たちから、つまり、考え方の異なる多くの人たちから受け容れられている必要があるのです。
要は人々の感情的な側面からの評価にも耐えるものとして政策は作られなくてはならないのです。私はこのようなことを「受容可能性」という概念で表現しています。
「政策が受け容れられている」とはどのような状態か?
では、政策が「受け容れられている」とはどのような状態なのでしょうか。「受容」とよく混同されがちな言葉として「選好=好き嫌い」と「支持」があります。この受容・選好・支持の違いを探りつつ、受容されている状態について考えてみたいと思います。
「好き嫌い」と「受容」:嫌いな食べ物も食べられはする
ところで、皆さんは嫌いな食べ物などはあるでしょうか。
私は小さいころからブロッコリーが苦手でした。口の中でのもそっとした感覚、嚙み砕いたときのぼそぼそ、ぶつぶつが口の中にいつまでも残る感覚が苦手です。が、食べられないほどではありません。もちろん飲食店で頼んだ料理にブロッコリーが混入していても素知らぬ顔して完食することができます。
つまり、私はブロッコリーという存在を「嫌って」はいますが、「受け容れる」ことはできるのです。なぜ、嫌いなものを受け容れられるのかはいろいろな要因が作用しています。例えば、大人として食の好き嫌いは恥ずかしいという社会的な体面もありますし、作ってくれた人に申し訳ないという他者への配慮、体に良いはずだという科学的な側面も作用しているでしょう。
ここに「好き嫌い」と「受容」の違いが見出せます。つまり、「好き嫌い」というのは「対象(=ブロッコリー)に対する個人的な評価」です。一方、「受容」というのは単なる「個人的評価」ではなく、社会的体面や他者の視点、社会的な言説などを含めた「対象(=ブロッコリー)に対する総体的な評価」といえるでしょう。
私たちは個人的に嫌いなものであっても、総体的には受け容れることが出来るのです。これは喜ばしい事実です。
「受容」と「支持」:食べられはするけど、自分では買わない
では、私はブロッコリーと全面的に和解できたのか?というと決してそうではありません。例えばスーパーに買い出しに行ったとき、私はまかり間違っても買い物かごにブロッコリーを入れることはしませんし、我が家でブロッコリー料理が出ることはありません。
つまり、私はブロッコリーを「受け容れる」ことはできますが、自分から能動的に行動を起こしてブロッコリーを食することを「支持」してはいないのです。
これが「受容」と「支持」の違いです。受け容れられていることを前提としたうえで、さらに能動的な行為が伴ったものが「支持」です。その意味では受容されていなければ支持されませんが、受容されているから支持されるというわけではないのです。
話をまとめましょう。私たちは個人的な感情として「好き嫌い」を持っていますが、例え「嫌い」なものであっても、他者の視点や社会的な事情を考慮して「受け容れる」ことが可能です。しかし、「受け容れている」から能動的な行為を伴う「支持」がもたらされるかというと、そうではありません。
つまり「受容」というのは「選好=好き嫌い」と「支持」の中間に存在する非常に広範な領域をカバーする概念なのです。これは政策であっても同じことです。もちろん、特定の政策が多くの人たちに「支持」されていることが最も好ましいことに違いありません、しかし、私たちには「好き嫌い」があります。すべての政策を心の底から歓迎することはできません。であれば、「嫌い」な政策であっても、少しでも「受け容れ」てもらう必要があるのです。ここに政策の「受容」を考える必要性が立ち現れます。
どのようにしたら受容されるか?
では、政策はどのようにしたら受け容れられるのでしょうか。
まず、受容を構成する要素については社会心理学などの領域である程度の研究蓄積があります。よく挙げられるものとしては、問題の認識(=なぜ、それが重要な問題なのか)、社会的圧力(=みんなはどう考えているか)、有効性の感覚(=どの程度の利益が発生するか)、公平性(=みんなが公平に扱われているか)などが個人の好き嫌いを超えた「受け容れ」を発生させる要因として指摘されています。
このように列挙された受容の構成要素を、現実問題としてどのように政策に織り込むか=どのようにしたら政策が受容されるか?というのが私の研究テーマです。
これは現在進行中の研究テーマになるので確定的なことは言えないのですが、理論的には①市民参加などの方法で「合意形成」を図るアプローチ、②政策担当者と住民間の日常的な接触と対面コミュニケーションに着目した「執行スタイル」アプローチ、③政策に関する情報提供に着目し、政策に対する社会的イメージを変更させる「問題の再定義」アプローチの三つを仮説として設けたうえでケーススタディを行っています。
これらの理論的フレームワークのもと、各自治体で制定され、その制定過程において社会的に「炎上」した条例・条例案を対象とした公文書や議事録などの分析を行っているところです。
さて、尻切れ蜻蛉感が否めませんが、そろそろ結びとします。
政策というと数的に把握できる「効果」がその成否を分かつ基準として考えられがちですし、私もその点を否定するつもりはありません。しかし、それだけではないのです。私たちがその生活のなかで何かの決定を行うとき、その決定の「効果」だけを考えているわけではないはずです。効果が出ずとも納得できる決定もありますし、効果が出ていても納得できない決定もあります。政策も人が作り、人の生活に関するものである以上、人間の感情や認識、価値観からは逃れられないのです。これらにきちんと向き合い、より複線的に政策を把握すること、これが私の研究テーマです。